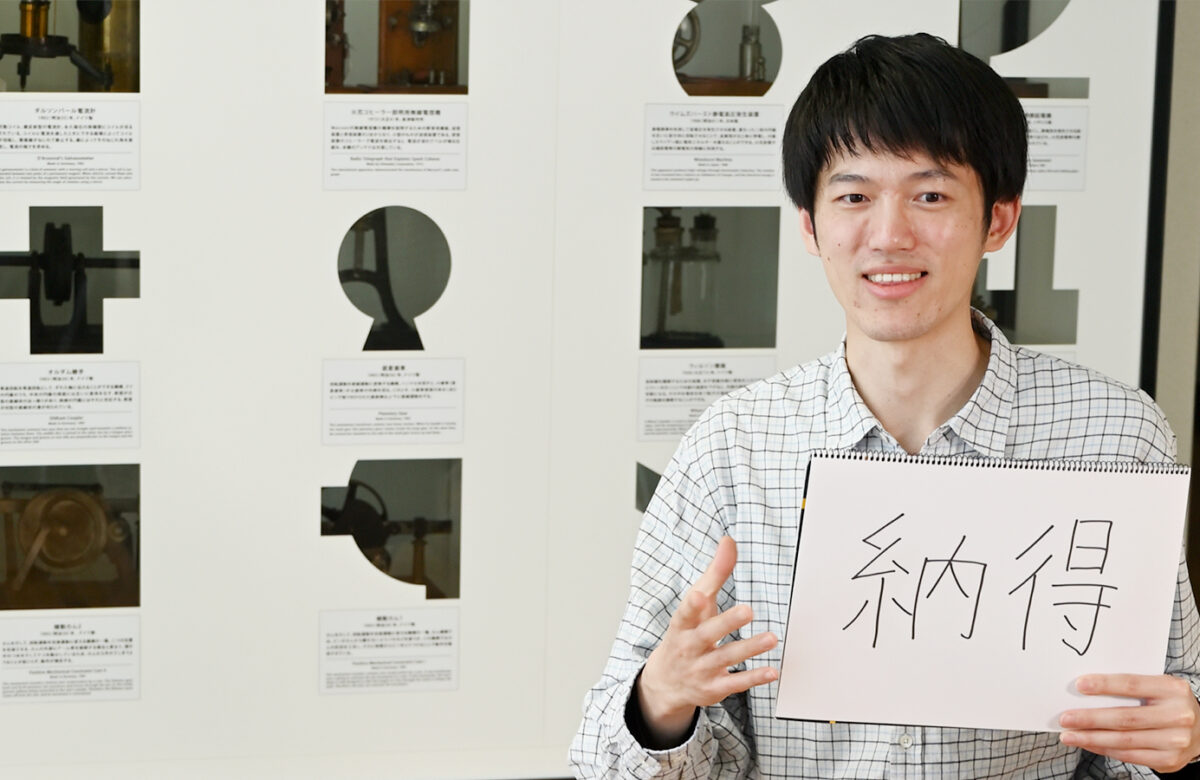ScienceTalksのウェブサイトが本日立ち上がりました!
- お知らせ日本語記事
- June 1, 2013
Science Talksとは、「ニッポンの研究力」を研究者・科学者のみなさんと一緒に考えていくためのプラットフォームです。Science Talksの発端は、この疑問から始まりました。
「ニッポンの研究力は果たして本当にこのままでいいのか?」
これまで、日本の研究・技術開発力は、戦後日本の経済発展を支える上で大きな役割を果たしてきました。しかし近年の研究論文投稿・出版の動向を見ると、日本の科学者・研究者の「研究力」は、欧米諸国をはじめ、近年力を付けてきている中国などのアジア諸外国の伸びに比較すると伸び悩んでいます。
日本の研究は、これからの競争を乗り越えていけるだけの十分なスタミナを備えているのでしょうか?
次のおよそ10年、20年、世界経済がダイナミックに変化する時代の中で、世界をリードする科学技術立国として、研究者や企業がイノベーションを出し続けていける環境に、果たして本当にあるのでしょうか?
「ニッポンの研究力」このままではいけない、と私たちは考えます。
10月19日(土)に開催される第1回のシンポジウムのテーマは「ニッポンの研究力を考える-未来のために今研究費をどう使うか-」。
研究力のそもそも論である、研究費の額と分配、研究評価の問題を徹底的に取り上げて議論をします。 また、こちらのサイトや、Science Talks公式ツイッターアカウントを通じて、みなさんのご意見をどしどしお待ちしています!!
さあ、みなさんご一緒に研究費について考えましょう!